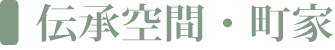飛騨高山の見どころ(伝承空間・町家)
|
飛騨の歴史民俗資料約7万5000点を所蔵。そのうち900点を常時展示する郷土史研究の拠点施設。建物は江戸時代から続く豪商永田氏が1875年(明治8)に建てた檜造りの土蔵を利用している。展示品は高山城主・金森氏に関する資料をはじめ、円空仏や酒造りの資料、美術工芸品などのほか、高山祭のからくり人形など広範囲に及ぶ。庶民の生活道具の展示も多く、特色ある高山文化の担い手だった町人文化を知ることができる。また、市内片野町の糠塚遺跡から出土した縄文前期の浅鉢形土器大小一対(重要文化財)も常設展示されている。所要30分。 |
|
|
高山城二の丸の登城門をモデルした、ユニークな入口が目印。高山在住の医師、藤井糺一[ただいち]氏が大正中期から約70年かけて集めた、安土桃山時代からの古美術品や民芸品約2500点を公開している。展示室は、壁の厚さが1m近くもある江戸萬流土蔵。5年をかけて建てられた。ここに享保雛[きょうほびな]など江戸時代の人形、一休禅師や富岡鉄斎、横山大観らの掛け軸、古九谷や古伊万里など多彩な展示品が並ぶ。所要30分。 |
|
|
飛騨の匠の伝統工芸である春慶塗の博物館。白壁土蔵造りの館内に、江戸時代から現在までの逸品数百点を展示。オリジナルの春慶塗作品を作ることができる絵付け体験も人気。 |
|
|
徳川幕府の代官所・郡代所の遺構。元は高山城主金森氏の屋敷だったが、1692年(元禄5)に天領(幕府の直轄領)になってから25代176年間、ここで飛騨の統治が行われてきた。門番所付きの重厚な御門は1832年(天保3)の建築。玄関之間、大広間、吟味所、白州、御役所、御用場は1816年(文化13)に改築された。年貢米を収めた御蔵8棟は1695年(元禄8)に高山城三の丸から移築したもので、築400年を経たわが国最古・最大の土蔵といわれる。門前の広場では毎日朝市が開かれる。所要30分。 |
|
|
高山で幕府相手の両替商と造り酒屋として手広く事業を行ってきた豪商。軒下には杉玉が下がり、酒造業時代の名残りをとどめている。現在の建物は、1907年(明治40)に当時の名棟梁西田伊三郎が建てたもので、国の重要文化財に指定されている。飛騨地方の町屋建築の様式を明確に保ち、完成された美しさで知られる。みどころは玄関を入った土間の吹き抜け空間。大黒柱を中心に、梁と束で幾何学的に組まれた木組の空間を造りあげ、高窓から差し込む光が美しいシルエットを描く。各部屋の造作にも粋をこらし、優美なたたずまいになっている。所要30分。 |
|
|
初代藩主の金森長近が1585年(天正13)に城下町を造営する際、浄土真宗の門徒の中心道場として白川郷から移築した寺。その後幾度か火災に遭い、現在の本堂は1964年(昭和39)に再建されたもの。寺宝館(希望すれば拝観は可能だが、15時まで。無料)には親鸞[しんらん]上人の一代記を描いた絵など、貴重な宝物100点余りが展示されている。また、庫裡は飛騨随一の豪農であった杉下家の民家を移築したものだ。 |
|
|
秋の高山祭の屋台を常設展示。巫女の説明を受けながら見学できる。飛騨の匠、金工、漆工などの技術を駆使した屋台は、11台すべてが国の重要有形民俗文化財に指定。祭りばやしが流れる館内には祭り装束の人形が配され、臨場感たっぷりだ。15分間のビデオで高山祭も見物できる。付設の桜山日光館では、大正時代に造られた日光東照宮の10分の1サイズ模型を展示。所要1時間30分。 |
|
|
桜山八幡神社境内にあり、神楽台など11台の屋台が、4台ずつ4カ月毎に入れ替えて展示している。また桜山日光館では、日光東照宮の10分の1の模型が展示されている。 |
|
|
天領時代に代官所の御用商人として栄えた日下部家の町屋住宅を利用した民芸館。奥の土蔵を展示室に使い、日下部家伝来の渋草焼の初期のものなど、美術品や民芸品を公開している。建物は男性的な力強い造りが特徴で、現在の建物は1879年(明治12)、飛騨の名棟梁川尻治助[かわじりりすけ]の手により、江戸時代の建築様式を忠実に伝えている。主屋は床面積が1502平方mの総檜造り2階建て。軒の出が深く、梁と束柱の力強い立体的な木組の吹き抜け空間や窓切りの変化など、高山の町屋建築の集大成といわれる。国の重要文化財。所要20分。 |
|
|
明和6(1769)年に「打保屋」の屋号でびんつけ油、ろうそくの製造販売をはじめた豪商平田家の屋敷を公開。代々集められた商売道具や生活用具の数々を展示。 |
|
|
高山出身の超心理学者・福来友吉[ふくらいともきち]博士の研究資料や遺品を展示。博士は1910年(明治43)に初めて念写(透視現象)の実験を行なった。館内には、超能力者が念写したという月の裏側の写真など、不思議な現象の資料を紹介している。所要30分。 |
|
|
明治28年から昭和43年まで使用された町役場・市役所の建物です。高山市三町伝統的建造物群保存地区内の南端にあって、一之町、二之町、三之町を見渡す重要な位置にあります。建築材は総檜で、官材を使用しており、ガラスも初めて導入され、硝子障子という名称で各所に使われています。 明治の高山町から現在の高山市までの行政資料を保存、展示しています。 |
|
|
建物の建築年代は1826年(文政9)と推定され、明治8年の大火を免れた貴重な江戸時代の町家。創建以来ほとんど手を入れていない貴重な住宅として国の重要文化財の指定を受けている。当時の建物の特徴をよく残し、2階の中庭に面して茶室が設けられています。かつては薬種商を営む屋号「原三」の店舗兼用住宅。明治45年には蝋燭、練油、金貸なども営んだ松本家のものとなっています。 |
|
|
明治8年(1875)の大火後に建てられた建物で、敷地は間口3間半のごく標準的な商家。奥行きは12間程度あり、母屋・中庭・土蔵と並んでいる。大新町周辺は越中街道沿いに開けた商人町であったこともあり、伝統的様式の町家が残っているが、なかでも宮地家は改造を加えていないとても貴重なものだ。屋号を「宮地屋」といい、かつては農業を営んでいた。 |
|
|
高山城主金森家の御典医(大名に勤めた医者)の住まいと伝えられています。戦国武家屋敷をしのばせるたたずまいで、吊天井や忍窓、井戸の抜け穴などが見られます。土蔵には飛騨の考古、歴史資料などを展示しています。 |
|
|
全国から集めた獅子頭を展示するほか、館内ではからくり人形の実演(1時間に2回、所要20分)などを行っている。江戸時代に作られた棒からくりは、「弁慶と牛若丸」を演じる。大黒様が獅子舞を舞う、糸からくりは3体、座敷からくりが1体ある。 |
|
|
高山城主金森家の御典医(大名に勤めた医者)の住まいと伝えられています。戦国武家屋敷をしのばせるたたずまいで、吊天井や忍窓、井戸の抜け穴などが見られます。土蔵には飛騨の考古、歴史資料などを展示しています。 |
|